器の取り扱い方

■高台の確認
器の高台のざらつきがないか、器を裏返して指で触れてご確認ください。高台のざらつきは食卓を傷つけます。もし、高台がザラザラしていたら、目の細かいサンドペーパーか砥石(といし)で丁寧にこすってなめらかにしておきます。
そしてぬるま湯で丹念に洗います。
シールやラベルのついているものははがしましょう。
はがしにくいときは、ぬるま湯の中にしばらく浸しておくとはがれます。
それでもはがれない時は、水気を拭いてドライヤーの温風を当ててみてください。のりがとけてはがしやすくなります。
■磁器の使い始め
磁器は熱めのお湯で充分に洗い流し、柔らかいスポンジなどで軽くこすってください。この時、色絵や金彩などを傷つけないように気をつけます。
■陶器の使い始め
焼締、粉引など、土ものといわれる陶器は、鍋に入れて器がかくれるくらいの水と米ぬかを入れて煮沸します。米のとぎ汁でもいいです。これで器の焼を堅く締めることになります。また土肌の目が詰まるので汚れがしみにくくなり、汁もれも防ぎます。
例外は低温度で焼かれた軟質陶器の楽焼。煮沸すると土目がもろくなって傷みやすいので、薄めた台所用洗剤とスポンジで洗い、
よくすすいで乾かします。
■陶器にお料理を盛るとき
お使いになる前に器に水を張ったり、水にくぐらせたりして表面に水を含ませた後、水分を軽く拭いてからお料理を盛り付けますと、色の染み込みや匂い移りがすくなくなります。料理を盛る前に水を含ませておきますと、驚くほどツヤのある料理映えのする器に変身します。
※特に粉引・焼締めの器はよく水を含ませてください。
※粉引の器は、使い方に気を付けていても長く使うほど貫入に色が入り染みになったりしていきます。
ですが、それが器を育て楽しみ、愛着となります。
■洗い方と普段のお手入れ
使い終わった器は早めに洗ってください。陶器は磁器に比べ弱いので付けおきをしない方がよいと思います。また、食器洗い機は大変便利ですが、面倒でも手で洗うようにして下さい。
最後にちょっと熱めのお湯をかけますと、曇らずにすっきりと乾き、後が楽です。
陶器は充分に乾いてから食器棚にしまってください。これをしないとカビが生えることがあります。
特に焼締のうつわには注意してください。
■カビが生えた時は
一度ついてしまったカビは残念ですが取り除くことは難しいです。陶器に生えてしまうカビは、黒いぼんやりとした点々がいくつか見えた状態です。
器の「鉄粉」の黒い点と間違えやすいのですが、違うことは臭いがします。
カビを付けないことが一番いいのですが、もしカビが生えてしまったら、
薄めた漂白剤に浸すと取れることがあります。カビが取れた後は、しっかりすすぎをして充分に乾燥させてください。
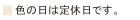
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
メルマガ登録
お買い物ガイド
お支払い方法
-
クレジットカード決済
クロネコWEBコネクトを採用しております。 -
銀行振込
ご注文後、5日以内に口座にお振込み下さい。
お振込み手数料はお客様ご負担です。 -
ゆうちょ振替
ご注文後、5日以内に口座にお振込み下さい。
お振込み手数料はお客様ご負担です。
送料・配送について
-
ヤマト運輸
16,500円(税込)以上お買い上げの方は、送料無料とさせていただきます。
16,500円(税込)未満お買い上げの方は、各都道府県により送料が異なります。
※日本国内の発送のみとなります。
※海外へ発送はしません。日本から海外への転送された商品の保証はしません。
破損・交換・返品について
交換、返品につきましては、商品到着後7日以内にメールまたは電話でご連絡をお願いします。
7日を経過してからの交換、返品は不可ですので、必ず到着時、商品に破損がないかご確認ください。
お問い合わせ
当店はオンラインショップのみです
- ≫お問い合わせ
- TEL: 0586436880
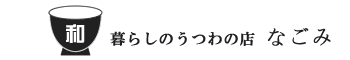
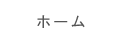
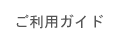
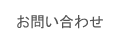
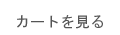


 安達 和治
安達 和治
 伊藤 みほ
伊藤 みほ
 伊藤 豊
伊藤 豊
 魚谷 あきこ
魚谷 あきこ
 鵜飼 菜月
鵜飼 菜月
 大久保 新
大久保 新
 尾形 アツシ
尾形 アツシ
 沖澤 真紀子
沖澤 真紀子
 小澤 基晴
小澤 基晴
 小山 乃文彦
小山 乃文彦
 掛江 祐造
掛江 祐造
 KANEAKI SAKAI POTTERY
KANEAKI SAKAI POTTERY
 河合 里奈
河合 里奈
 木村 扶由子
木村 扶由子
 坂口 未来
坂口 未来
 柴田 サヤカ
柴田 サヤカ
 杉江 善次
杉江 善次
 高山 愛
高山 愛
 田鶴濱 守人
田鶴濱 守人
 田鶴濱 優香
田鶴濱 優香
 谷口 晃啓
谷口 晃啓
 谷村 仁美
谷村 仁美
 塚本 友太
塚本 友太
 辻本 路
辻本 路
 角田 武
角田 武
 南部 恭子
南部 恭子
 額賀 円也
額賀 円也
 原田 晴子
原田 晴子
 増田 エミ
増田 エミ
 村井 陽子
村井 陽子
 山中 勇人
山中 勇人

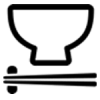 アイテム
アイテム
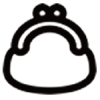 価 格
価 格

